一人親方労災保険には有効期限があるため、更新が必要です。
労災保険の期限が切れてしまうと、資格が失効となり、補償が受けられなくなってしまいます。
毎年3月末には労災保険の更新手続きを行い、不測の事態を回避しましょう。
今回は、一人親方労災保険の有効期限や更新方法、更新しないリスクや注意点について解説します。
一人親方労災保険で補償が受けられるように、本記事を参考に加入状況を見直してみてください。

Contents
一人親方労災保険は更新しなければならない?
一人親方労災保険の適用期間は、4月1日〜翌年3月31日の1年間で、毎年更新手続きが必要です。
年の途中で加入した場合でも有効期限は変わらず、加入日から翌年の3月31日までとなります。
更新手続きをしないと次年度から労災補償が適用されないため、更新忘れに注意しましょう。
ただし、一人親方労災保険の加入は義務ではなく任意のため、更新するかしないかは一人親方の意思で自由に決められます。
一人親方労災保険の更新方法や手順
一人親方労災保険を更新するには「新年度更新手続き」を行う必要があります。
一人親方労災保険の更新方法は、以下の通りです。
1.1月〜3月上旬に特別加入団体から更新案内が封書で届く
2.年度更新の案内を読み、期日までに1年度分の労災保険更新費用を支払う
3.新年度の有効期限が記載された新しい組合員証や加入証明書が発行される
新年度も継続して加入する場合は、更新の案内が送付されたら、忘れずに更新手続きを行いましょう。
一人親方労災保険の更新に必要なもの
一人親方労災保険の更新に必要なものは、以下の通りです。
- 申請書(更新の案内に同封)
- 更新費用
- 各種振込用紙
- 健康診断書(新たに特定業務に従事するようになった場合)
労災保険の加入時に健康診断を受けていれば、年度更新時に健康診断を受ける必要はありません。
しかし、年の途中で新たな特定業務を行うようになった場合は、改めて健康診断が必要な場合があります。
健康診断が必要な場合
一人親方が労災保険に加入する場合、特定業務と従事期間によっては申請時に改めて健康診断が必要です。
特に、以下の表に該当する特定業務を年の途中で行うようになった場合は、注意しましょう。
健康診断証明書を提出せずに、業務内容や業務歴について虚偽の報告を行うと、補償が受けられない可能性があります。
健康診断が必要な特定業務と従事期間は、以下の通りです。
| 業務の種類 | 従事期間 | 必要な健康診断 |
| 粉じん作業 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
| 振動工具使用 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
| 有機溶剤業務(屋内) | 6ヶ月以上 | 有機溶剤健康診断 |
一人親方労災保険の更新費用
一人親方労災保険の更新の際に支払う費用は、1年間分の組合費と労災保険料です。
加入団体によって更新手数料がかかる場合もあるため、詳細は加入団体に問い合わせたりホームページで確認したりしましょう。
また、加入団体によって、銀行振込やコンビニ振込、クレジットカードなど支払方法が異なります。
特に、銀行振込の場合は名義を間違えてしまうと正しく送金できないため、注意が必要です。
労災保険更新費用の振込は「請求書に記載される管理番号+加入者」で行いましょう。
労災保険料
給付基礎日額によって算出される労災保険料は、一般的に平均賃金に相当する額を設定します。
収入が一定ではない一人親方は、自分で考えて給付基礎日額を設定することが大切です。
給付基礎日額を高く設定すると、労災保険料も高くなり、手厚い補償を受けられます。
組合費
組合費とは、主に労災保険特別加入団体の運営のために支払う費用です。
組合費は毎月必要で、団体によって金額に差があるため、組合費を比較して加入する団体を決めるとよいでしょう。
一人親方労災保険の特別加入は国の制度のため、どの団体も労災保険料と補償内容は変わりませんが、加入団体によっては飲食店や施設などで優待を受けられるようです。
一人親方労災保険を更新できなかった場合はどうなる?

もし、一人親方労災保険を更新できなかった場合は、3月末日で強制脱退手続きが行われ、労災保険が失効となります。
脱退日の翌日以降の労災保険の補償は対象外となるため、期限切れには注意しましょう。
また、無保険となったことで、現場へ入場できない可能性があります。
業務に支障をきたさないためにも、未加入状態にならないことが大切です。
更新できなかった場合の対処法
一人親方労災保険を更新できなかった場合の対処法としては、「再加入手続き」を行います。
「再加入手続き」は、最短でも手続きした翌日からの加入となるため、手続きの期間中は労災保険未加入の状態です。
手続き期間中に災害に遭っても、労災保険給付に関する補償は受けられないため、注意しましょう。
また、脱退の申請を忘れてしまった場合は、脱退の理由が「未払いのための強制脱退」とみなされてしまいます。
そのため、継続加入しない場合は「脱退の申し出」を期限内に必ず行うことが大切です。
一人親方労災保険の更新に関するよくある質問
一人親方労災保険の更新に関するよくある質問についてまとめました。
一人親方労災保険の加入団体を変えたい場合の手続きは?
加入団体を変更する場合、現在加入している団体へ「退会届」を提出し、新たに加入する団体へ「加入申請書」を提出して組合費や保険料の支払いを行いましょう。
一人親方労災保険に年度加入する場合の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までです。
加入時期が月初めか月の途中かに関わらず同額の納付金を支払います。
月割り計算として、月の途中で脱退しても1ヶ月分が徴収されるため、加入団体を変更する場合は、現在の団体を月末に退会し、新たに加入する団体は月初めに入会するとよいでしょう。
加入団体によって組合費や入会金などの費用が異なることから、更新時により費用の安い団体へ乗り換えることで更新費用を抑えることができます。
労災保険特別加入の更新時にできる手続きは?
労災保険特別加入の更新時にできる手続きは、給付基礎日額や登録情報の変更です。
給付基礎日額は、収入が一定でない一人親方の場合、前年度の年収を考慮して定期的に見直し、給付基礎日額を自分で設定するとよいでしょう。
また、住所や戸籍などの登録情報の変更も併せて行うことができます。
更新手続き後に送られる加入証明書を受け取るためにも、住所変更が生じた場合は忘れずに登録情報の変更を行いましょう。
短期加入の場合も更新できる?
数ヶ月だけ加入する「短期加入」の場合は、基本的に脱退扱いとなります。
延長を希望する場合は、延長の申込や費用入金などの手続きが必要となるため、早めに手続きをしましょう。
延長の申込は、公式HPやメール、電話など各種加入団体によって異なります。
一人親方労災保険を更新した後に途中で脱退できる?
一人親方労災保険への加入は任意のため、更新後に途中で脱退することは基本的に可能です。
年の途中での脱退は、月単位で保険料を計算し、すでに支払った費用が返還されます。
一般的に、組合費や入会金は返還をしない団体が多いものの、保険料をまとめて支払っている場合は返金されます
保険料の返金があった場合は、勘定科目の仕訳を「雑収入」として会計処理する必要があります。
加入者証の返還方法や返金額や返還時期、脱退方法については各加入団体によって条件が異なるため、確認してください。
一人親方労災保険の加入は労働局承認一人親方団体労災センターへ
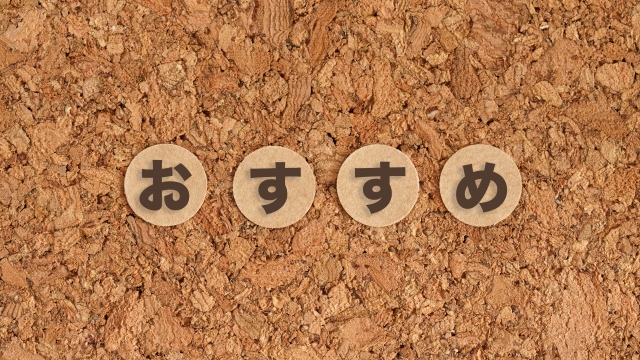
一人親方団体労災センターは、加入証明書の即日発行や最短翌日加入も可能で、年度加入と1ヶ月・2ヶ月のみの短期加から選択できます。
加入時にかかる費用は、3500円~2万5000円の給付基礎日額(16段階)×加入月数と、組合費が月500円(年度加入の場合)で、初年度のみ入会金1000円がかかります。
また、団体割引もあり、労災保険番号の連絡や、一人親方を労災保険に加入する手続きも可能です。
労災申請書類は追加費用なく当センターが作成するため、万が一の労災事故の場合に安心して補償を受けたい一人親方はぜひ加入をご検討ください。
まとめ
一人親方労災保険は、毎年度3月末に更新手続きを行う必要があります。
加入団体から更新の案内が届き次第、期日までに保険料を支払い、次年度の更新手続きを行いましょう。
一人親方労災保険の有効期限が切れると、補償を受けられないため、速やかに更新手続きを済ませることが大切です。
また、業務内容が途中で変わった場合は、改めて健康診断を受けなければならないケースがあります。
今回紹介した健康診断の条件や各団体からの案内をよく確認し、一人親方労災保険を更新するタイミングで給付基礎日額も見直すとよいでしょう。
