一人親方として働くうえで、建設業での一人作業が禁止されているのか気になる方も多いのではないでしょうか。
一人作業は法律では禁止になっていませんが、建設業においてはリスクが潜んでいます。
今回は、建設業で一人作業が危険といわれる理由について解説していきます。
また、一人作業が多い一人親方にとって、安全に作業を行うためのポイントもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

Contents
建設業で一人作業は禁止されている?
建設業における一人作業は、法律で禁止されているわけではありません。
ただし、事業者に対して、労働安全衛生規則等では作業環境や作業管理に関する事項が義務付けられています。
作業を請け負う一人親方は、一人作業のリスクを理解したうえで作業する必要があります。
建設業の一人作業に法的根拠はないが安全配慮義務がある
企業は、雇用人数に関係なく、労働者が安全で健康に労働できるように配慮することを労働契約法で義務付けられています。
一人作業中に労働災害が発生すると、会社側に安全配慮義務違反が認められるケースが多いです。
会社に安全配慮義務違反が認められる場合は、被害者側は会社に対して慰謝料や損害賠償の請求ができます。
建設業で一人作業が危険といわれる理由

建設業の年間事故件数は、厚生労働省「令和5年の労働災害発生状況を公表 」によると、建設業が最多で、製造業、陸上貨物運送事業と続きます。
建設業の労働死亡災害割合は約30%を占めており、建設業は事故のリスクが多い業種といえるでしょう。
中でも、「墜落・転落」「挟まれ・巻き込まれ」事故が多く、死亡事故リスクは非常に高くなっています。
また、墜落・転落災害の死亡者数の割合は、38.6%の一般労働者に対し、一人親方は63.8%と約1.6倍です。
建設業で一人作業が危険といわれる理由について解説していきます。
想定外のアクシデントへの対応が困難なため
建設業で一人作業が危険といわれる理由は、想定外のアクシデントへの対応が困難なためです。
一人作業中にアクシデントや事故が発生した場合、発見が遅れてしまい、対応が遅れて命に関わるリスクがあります。
特に、事故や急病時には素早い対応が必要です。
たとえば、事故が起きて身動きが取れない状況の場合、周りに人がいないため、発見が遅くなるなどが挙げられます。
想定外の事故に遭遇すると正常な判断が難しいため、周りに人がいることで冷静に対処しやすくなるでしょう。
作業を省略して業務フローから逸脱するリスクがあるため
建設業で一人作業が危険といわれる理由は、やるべき作業を省略して業務フローから逸脱するリスクがあるためです。
一人作業では周囲の目がないため、定められた作業手順を省略し、確認作業を怠るケースがあります。
特に、急いでいることを理由に通常とは異なる手順で作業をしてしまうと、大きな事故を引き起こしかねません。
作業管理不足に陥りやすく、労働災害につながるリスクが高い一人作業では正確な手順を守りましょう。
作業に慣れが生じて危険性が軽視されるため
建設業で一人作業が危険といわれる理由は、作業に慣れが生じて危険性が軽視されるためです。
慣れが生じると、経験から作業の危険性を軽視して誤った自己判断をしがちです。
危険を軽視した行動は、些細なミスにつながり、重大事故を引き起こしてしまいます。
たとえば、高所作業での安全対策装備の未着用といった、規定の確認作業を怠るケースなどです。
特に、新人やベテランの作業者は慣れてくると作業の危険性を軽視しやすいため、注意する必要があります。
過労による集中力の欠如でミス発生のリスクがあるため
建設業で一人作業が危険といわれる理由は、過労による集中力の欠如でミス発生のリスクがあるためです。
疲労が溜まると誰しもさまざまな能力が低下し、思うように身体や頭が働かないことがあります。
特に、一人作業はほかの人と話すことなく、業務に集中してしまい、十分な休みがとれずに作業を続けることもあり、過労に陥りやすくなります。
過労状況に気づかず、夜間や長時間労働に臨むと心身に大きな負担をかけて、ミスを発生させてしまうでしょう。
また、気温が高い夏場は熱中症に注意が必要です。
疲労によって注意散漫になり、周りが見えなくなる前に、適度に休憩をとり、長時間労働を緩和することが大切です。
集中力の低下による不注意から事故を起こさないためにも、疲れを溜めないように定期的にリフレッシュしましょう。
建設業の一人作業で事故が発生した事例
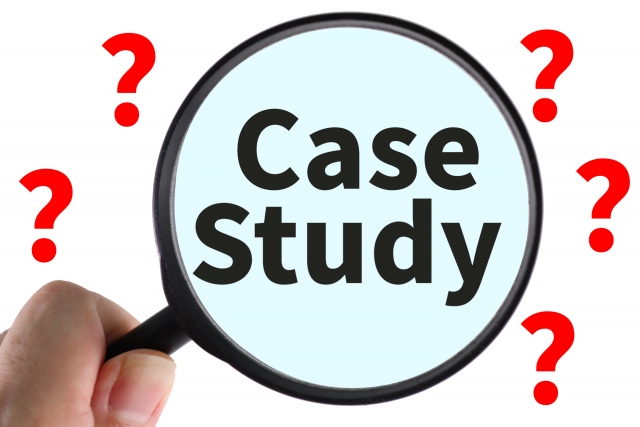
建設業の一人作業で事故が発生した事例について2つご紹介します。
一人作業の事故事例|建築工事業
| 発生時期 | 令和4年1月 |
|---|---|
| 被災者(経験年数) | 70歳代(30年以上) |
| 事故の種類 | 墜落・転落 |
| 被害状況 | 頸椎骨折により死亡 |
| 事故の概要 | マンション建設現場1階で、一人作業をしていた型枠解体作業従事者が、脚立の横で意識不明の状態で倒れていた。 |
| 事故原因 | 不明(脚立から転落か、地面で転倒か) |
出典:厚生労働省「令和4年建設業死亡災害事故事例 」
上記の事例のように、一人作業が死亡につながったケースもあります。
発見までに時間がかかった可能性があるうえに、事故の詳しい原因が判明しなかったことなど、複数人で作業していれば防げた可能性があるでしょう。
一人作業の事故事例|ビルメンテナンス業
| 発生時期 | 平成26年10月午後4時頃 |
|---|---|
| 被災者(経験年数) | 72歳男性(11年4か月) |
| 事故の種類 | 墜落・転落 |
| 被害状況 | 頸椎骨折により死亡 |
| 事故の概要 | マンション管理員が日差しよけのビニールシートのずれを直す作業を、脚立を設置して一人作業した。 高さ約5mの高所作業を補助者不在で梁に登った直後に地面へ転落した。 |
| 事故原因 |
|
出典:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会「災害発生報告・事例集 」
先ほどの例と同じく、はしごや脚立などで一人作業をした際に実行が発生するケースは多く報告されています。
はしごや脚立での事故を防ぐためには、「固定する」「ほかの人が下で支える」などの対策が重要でしょう。
一人作業を安全に行うための対策とポイント

建設業において一人作業を安全に行うことは労働災害を防ぐうえで重要です。
一人作業を安全に行うための対策とポイントについて4つ解説します。
作業に関する技術や安全装備に関する知識の習得
一人作業で身を守るためには安全性の高い装備や設備が必要です。
現場に必要な装備や設備に対応するためにも、安全装備の装着方法や作業技術、知識の習得も重要なポイントです。
技能講習や特別教育が必要な作業を行う場合は、事前に必要な資格や免許を必ず取得しましょう。
一人KY活動の実行と安全意識の向上
一人作業では、より厳密に安全意識を向上させることが重要です。
危険予知能力を向上させるためにも、作業の危険度を点数化する「リスクアセスメント」の手法を取り入れるとよいでしょう。
そこで、一人KY活動を積極的に実行することで、危険要因の有無を確認して現状の把握ができ、危険ポイントを決めて目標設定ができます。
現地での一人KY活動の一環として、以下の自問自答内容10項目を参考にしてください。
- 墜落・転落しないか?
- 挟まれ・巻き込まれないか?
- 切れ・こすれないか?
- 転ばない・つまずかないか?
- 崩れない・倒れないか?
- ぶつからないか?
- 腰を痛めないか?
- 感電しないか?やけどしないか?
- におわないか?
- 異物が目に入らない・保護具を正しくつけているか?
指差し呼称で持ち場の点検
KY活動に加えて、指差し呼称で持ち場の点検をすることも一人作業を安全に行うための対策として有効です。
危険なポイントを決めて指差し呼称を行うことで、集中力を維持して作業に取り組むことができます。
特に、作業開始前の指差し呼称点検は、現場の不具合を発見することもあり、大きな声を出さなくても指と目視で、持ち場を客観的に点検しましょう。
IT機器の活用でリスク低減
一人作業を安全に行うためには、リスクヘッジとしてITの活用も一つの方法です。
IT機器の活用によって、警報システムや緊急対応の体制が整い、重大事態の発生時にも迅速に助けを求めることができます。
実際に、監視カメラによる作業者の状況把握や、転倒センサー機器で異常を検知して警報発令、ウェアラブルデバイスを装着した作業員の体調をリモートで一括管理などが行われています。
一人作業中に発生した事故のリスクは、作業者自ら助けを求められない状態に陥りやすい点です。
作業場所や作業員の状態を可視化して、作業環境の一元管理が行うことで、事故が発生した際に外部の人間が早く状態を把握して対応できるでしょう。
一人作業に関わる2025年4月労働安全衛生法改正とは
厚生労働省によると、2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、保護措置の義務付け対象が拡大し、請負人への保護具等の使用に係る周知が義務付けられました。
新たに義務付けられた主な改正は以下の2点です。
- 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置対象範囲を作業従事者全てに拡大
- 危険箇所等の例外的作業で保護具等を使用する請負人(一人親方、下請業者)に対する周知
また、以下の場面では、事業者が請負人に対して保護具の使用や特定の作業手順、作業方法による旨を周知することが推奨されています。
- 作業に応じた適切な保護具等の使用が義務付けられている場面
- 特定の作業手順や作業方法による作業が義務付けられている場面
まとめ
建設業において一人作業は法的に禁止されているわけではありません。
しかし、一人作業はリスクを伴うため、危険とされる理由について理解する必要があります。
特に、一人親方は不安全行動を注意される機会が少なく、現場に途中から入退場するスポット作業や一人作業が多いため、当日の注意事項や安全指示を必ず守って作業することが大切です。
また、新規入場者教育の受講や作業技術や道具に関する十分な知識を持って作業に取り組みましょう。
