安全衛生に関する知識を得る機会が少ない一人親方にとって、職長教育の必要性を感じない方もいるかもしれません。
しかし、一人親方にも「職長・安全衛生責任者教育」を受けることを現場への入場条件としているケースは多く、受講することが推奨されています。
労災事故が多い建設業において、職長は労働者の健康と安全を確保する大切な立場です。
今回は、一人親方にも関わる職長教育について、似た役割を持つ安全衛生責任者との違いや職長教育内容について解説します。
実際に事業者が行う職長教育の事例についてもぜひ参考にしてください。

Contents
そもそも職長教育とは?
職長教育とは、建設業や製造業において現場の監督やリーダーを担う人に必須の資格です。
職長教育を受けて修了証を交付されることで職長として認められます。
職長とは、事業場や作業所などにおいて労働者を指揮監督する人物のことを指し、各現場に1人は設置する必要があります。
大規模な建設現場で作業を行う場合は、複数のグループごとに職長の配置が必要なケースもあるでしょう。
職長教育は労働安全衛生法で規定
職長教育は労働安全衛生法第60条で、事業者は職長等に対して職長教育(安全衛生教育)を行うように規定されています。
厚生労働省は「元方事業者による建設現場安全管理指針」により、安全衛生責任者の氏名、駐在状況などを把握するよう事業者に求めています。
また、職長教育は初任時以降、5年毎の定期的な再教育が必要とされるほか、機械設備の変更時に受講が必要です。
元方事業者は、職長や安全衛生責任者が現場に入る前に教育や再教育を受けているか確認する必要があるでしょう。
職長の役割
職長の役割は、工場や建設現場での安全確保と現場で指揮をとり、全体を監督することです。
具体的には、作業手順の策定や改善、作業者の適正配置や教育、危険行為に対する指導などがあります。
主に、安全に正しく作業を行う対策や災害発生時には措置を講じる役割があり、労災事故が多い建設現場などで現場全体への指示出しや監督業務を担っています。
職長と安全衛生責任者との違い
基本的に職長と安全衛生責任者は兼務することが多く、厚生労働省は「職長・安全衛生責任者教育」として統合して実施を推進しています。
職長と安全衛生責任者の違いは、おもな業務内容が対内的か対外的であるかです。
職長は、作業員への作業手順の説明や労働災害防止のための安全管理など、おもに現場管理業務を行います。
一方、安全衛生責任者は元方事業者や統括責任者、請負人との調整や連携など対外的な管理業務を行います。
一人親方は職長教育を受けていなければならない?
一人親方は必ず職長教育を受けていなければならないのでしょうか。
結論としては、一人親方の場合も書類上では安全衛生責任者の設置は求められるため、職長教育と安全衛生責任者教育は必要です。
また、安全性を考え、現場によっては「職長・安全衛生責任者教育」を受けていない作業員の現場への入場を認めない場合があります。
現場に入るためには職長教育を受ける必要がある?

職長教育と安全衛生責任者教育は、法律的に全員が必要とされる資格ではありません。
しかし、現場に入るために職長教育を受ける理由は、全員が資格を持っていないという状況を作らないためです。
万が一、全員資格を持っていない状況で事故が起こった場合は、法律違反として大きな問題になる可能性があります。
特に大規模な現場では、入れ替わりの多い作業者の状況を把握することは難しいため、全員が資格を持つことで資格保有者が常にいる状況を維持しています。
職長教育はどこで受けたら良いの?
職長教育は、講習会・出張講習・Web講習などで受講できます。
職長教育の受講方法の各特徴を以下にまとめました。
| 受講方法 | 特徴 |
| 講習会 |
|
| Web講座 |
|
| 出張講習 |
|
企業であれば講習会や出張講習などを活用するケースがありますが、一人親方が職長教育を受講する際は、Web講習がおすすめです。
Web講習は、自宅にいながらでも受講できるため、場所や時間の制約がありません。
職長教育の内容
職長教育は合計14時間にわたる講習を2日間かけて受講します。
職長・安全衛生責任者教育の内容は以下の通りです。
| 種別 | 学科内容 | 講習時間 |
| 職長教育 | 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 2時間 |
| 労働者に対する指導又は監督方法に関すること | 2.5時間 | |
| 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること | 4時間 | |
| 異常時等における措置に関すること | 1.5時間 | |
| その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 | |
| 安全衛生責任者教育 | 安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
| 統括安全衛生管理の進め方 | 1時間 | |
| 合計(時間) | 14時間 |
出典:一般財団法人 中小建設業特別教育協会「職長・安全衛生責任者教育 講習会のご案内」
職長等の能力向上教育に準じた教育カリキュラム
職長は、職長教育を受けた後、能力向上教育に準じた教育を定期または随時受ける必要があります。
事業者は「安全衛生教育等推進要綱」に基づき、建設業の職長等の能力向上を図る自主的な安全衛生活動の促進が求められています。
厚生労働省が定める建設業での労働災害防止のために必要な教育カリキュラムの一例は以下の通りです。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
| 職長等として行うべき労働災害防止に関すること | 建設業における労働災害発生状況 | 90 分 |
| 労働災害の仕組みと発生した場合の対応 | ||
| 作業方法の決定及び労働者の配置 | ||
| 作業方法の決定及び労働者の配置 | ||
| 異常時等における措置 | ||
| 安全施工サイクルによる安全衛生活動 | ||
| 職長等の役割 | ||
| 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 労働者に対する指導、監督等の方法 | 60 分 |
| 効果的な指導方法 | ||
| 伝達力の向上 | ||
| 危険性又は有害性等の調査等に関すること | 危険性又は有害性等の調査の方法 | 30 分 |
| 設備、作業等の具体的な改善の方法 | ||
| グループ演習 ※右項目のうち1つ以上実施 |
災害事例研究 | 130分 |
| 危険予知活動 | ||
| 危険性又は有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置 |
出典:厚生労働省「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」
安全衛生教育フローの一例
安全衛生教育はどのような流れで行われるのでしょうか。
以下は、厚生労働省「安全衛生教育等推進要綱」 を参考にした、安全衛生教育フローのイメージ例です。
<安全衛生教育フローの一例>
| 入社:雇入時教育 |
| ↓ |
| 就業制限業務に配置転換:免許取得 |
| ↓ |
| 5年経過:危険有害業務従事者教育(定期) |
| ↓ |
| 10年経過:危険再認識教育 |
| ↓ |
| 職長就任:職長等教育 |
| ↓ |
| 5年経過:能力向上教育に準じた教育 |
| ↓ |
| 安全衛生推進者就任:能力向上教育(初任時) |
| ↓ |
| 5年経過:能力向上教育(定期) |
職長教育の事例
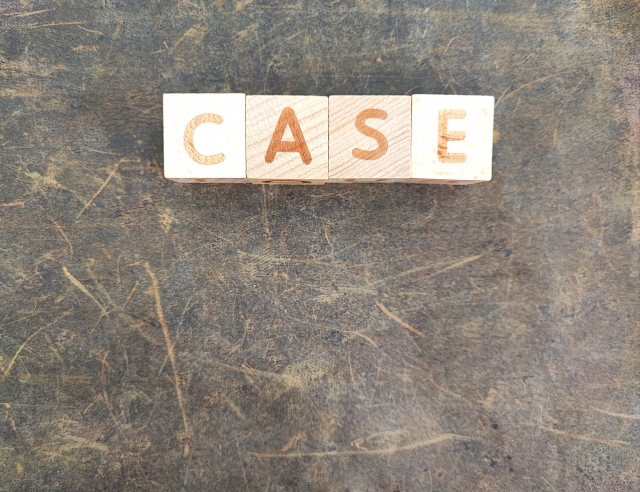
実際に、職長教育はどのように行われているのでしょうか。
職長教育の事例について「次代の安全の中核を担う人材育成 好事例集」 より抜粋して3つご紹介します。
職長教育の事例|建設業・とび工事業
東京都の加濃建設株式会社は、危険な作業が最も多い職種とび職に特化した教育を行い、労働災害の撲滅に努めています。
また法定の職長教育のほか、安全・施工管理教育の実施や安全衛生教育の柱として職長・作業主任者研修会を春と秋に年2回実施し、加えて独自の職長認定制度を導入しています。
職長認定制度は、法定の職長教育修了者の中から、自社基準に通達者を評価委員会で審査して適格な職長を社長が認定する取り組みです。
各現場に職長認定者を任命し、安全衛生のレベルアップを図っています。
職長教育の事例|左官工事業
神奈川県の進和工業株式会社は、毎月1回災害事例を用いた職長教育を行い、危険予知能力の向上と災害ゼロを目指しています。
たとえば、足場からの転落やミキサーの回転部に軍手を挟んでケガを負うなど、実際の災害事例をもとに原因や対策を考えさせる取り組みです。
また、KY(危険予知)活動の一環としてKYシートを活用し、危険が潜むポイントを探すトレーニングを何度も実施し、職長の危険予知能力向上に努めています。
さらに、特別教育や技能講習の実施にも力を入れ、作業員ほぼ全員が高所作業車、巻き上げ機、粉じんなどの必要な資格を取得済みです。
建設業労働災害防止協会のビデオ教材を活用して、職長や作業員の安全意識の向上を図り、不安全行動の撲滅に取り組んでいます。
職長教育の事例|紙加工品製造業
岩手県の北上ハイテクペーパー株式会社(現在は三菱製紙株式会社に吸収合併)は、職長教育を行う自前の2人の講師によって、場内の作業形態を考慮した教育内容を実現しています。
該当者の職長教育受講修了後は、約5年の組長経験者を対象に再受講を予定するなど、安全意識の向上を連綿と繰り返し、次世代の人材育成を目指した職長教育を進めることも特徴的です。
誰が担当しても継承できる体制で、ルールを守らなければ叱る「しつけ」をプラスした5S活動を徹底し、常に検証を心がけた安全ルールをいかに全員に知らせて徹底させるかに注力しています。
具体的には、テキストは見開き左側に法令、右側には事例を掲載する工夫を施し、危険予知トレーニングでは、安全衛生指導員全員に外部KYTトレーナー講習を受講させ、協力会社含む全従業員に講師としてKYT教育を行っています。
まとめ
建設業において、現場入りする際に職長教育を受講した資格がなければ入場できないケースがあるため、一人親方であっても職長教育は必要です。
職長と安全衛生責任者は兼務することが多く、講習が統合されたことから、職長教育と安全衛生責任者教育どちらも受講しましょう。
一般的な職長教育は2日間で受講修了後に資格取得となり、5年ごとの再教育を厚生労働省が定めています。
労働災害が多い建設業において、職長や安全衛生責任者の役割を理解し、安全衛生の向上に努めましょう。
