「定額減税は一人親方も対象になるの?」
「定額減税の手続きは難しい?」
「従業員を雇用している場合はどうなる?」
2024年6月から導入された定額減税について、手続き方法がわからずに不安な方も多いことでしょう。
定額減税は個人事業主である一人親方も対象であり、基本的に確定申告で定額減税の手続きを行います。
今回は、定額減税で減税される金額や手続き方法について解説します。
一人親方で扶養家族がいる場合や従業員を雇用している場合でも、定額減税手続きを検討している方は、本記事を参考にしてください。

Contents
定額減税とは?
定額減税とは、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が一時的に減税される制度です。
デフレ対策の一環として、2024年6月から始まりました。
住民税は、所得に応じた負担を求める「所得割」と所得に関係なく定額で負担する「均等割」があり、定額減税で住民税は「所得割」のみ減税されます。
また、対象範囲内の扶養家族がいる場合も、1人あたり所得税3万円、住民税1万円が減税されます。
ただし、定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除などのすべての控除が行われた後の所得割額から減税されるため、注意しましょう。
定額減税の目的
定額減税の目的は、物価上昇への対応として所得増加を図ることです。
定額減税制度の創設には、賃金の上昇が伸び悩む中で物価上昇により、家計を圧迫している背景があることから、政府は「給付」ではなく「減税措置」を打ち出しました。
定額減税の対象者
定額減税は、一人親方をはじめ、業種や働き方を問わず、年金受給者や事業所得者など多くの国民が対象です。
<定額減税の対象者>
- 2024年分所得税の納税者かつ国内居住者
- 2024年分の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの方は給与収入が2,000万円以下)
※ 子どもや特別障害者を有する者など、所得金額調整控除を受ける方は2,015万円以下が対象
定額減税の扶養家族の範囲
定額減税の扶養家族の対象範囲は、同一生計配偶者と16歳未満の扶養親族を含む合計所得が48万円以下(年収103万円以下)です。
同一生計配偶者とは、国内に居住する納税者と生計を一にする配偶者のことです。
また、扶養親族とは、納税者と生計を一にしている国内に居住する配偶者以外の親族を指します。
ただし、合計所得が48万円以上の場合は、本人が定額減税を受けることになります。
税法上の所得税や住民税における扶養控除では16歳未満は対象外であり、定額減税の扶養家族とは対象範囲が異なる点に注意が必要です。
一人親方も定額減税を受けられるの?
一人親方も個人事業主であり、定額減税を受けられます。
定額減税は、所得税や住民税が非課税の場合も救済措置を受けられるため、同一生計配偶者や扶養親族も同様に定額減税を受けられます。
<定額減税制度の減税額>
- 本人(居住者に限る):所得税3万円+住民税1万円
- 同一生計配偶者または扶養親族 (居住者に限る):1人につき所得税3万円+住民税1万円
扶養家族がいる場合、減税される金額は以下のイメージです。
<例1>3人家族の場合(一人親方・専業主婦・扶養対象の子ども1人)
| 本人 | 扶養家族 | 合計 | ||
| 妻 | 子ども | |||
| 所得税 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 9万円 |
| 住民税 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 3万円 |
| 合計 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 12万円 |
<例2>4人家族の場合(一人親方・専業主婦・扶養対象の子ども2人)
| 本人 | 扶養家族 | 合計 | ||
| 妻 | 子ども | |||
| 所得税 | 3万円 | 3万円 | 6万円 | 12万円 |
| 住民税 | 1万円 | 1万円 | 2万円 | 4万円 |
| 合計 | 4万円 | 4万円 | 8万円 | 16万円 |
一人親方が定額減税を受ける方法【所得税編】

定額減税の手続きは、基本的に確定申告で行い、年間の所得税が15万円以上の場合は予定納税で行います。
所得税と住民税で手続き方法が異なるため、一人親方が定額減税を受ける方法について、確定申告と予定納税それぞれ解説します。
確定申告
確定申告は、1年間の所得金額を税務署に申告する納税手続きです。
申告期間は、例年2月中旬から3月中旬となりますが、2024年分の確定申告は、2025年2月17日から3月17日までです。
所得は、確定申告書第一表の「所得金額等の合計⑫」欄に収入から費用や経費を控除した金額を記載します。
給与所得者である会社員は2024年6月から控除されるのに対し、一人親方は、翌年の確定申告後に控除を受けられるため、タイミングがずれる点に注意しましょう。
扶養家族がいる場合は扶養家族の人数を記載して提出
扶養家族がいる場合は、確定申告書に扶養家族の人数を記載して提出します。
扶養家族分の定額減税は、確定申告を通じて税額に落とし込まれる仕組みです。
予定納税
予定納税とは、前年分の所得金額や税額をもとに計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合に、一部の所得税を先に納付する制度です。
予定納税での定額減税は、年間予定納税額の3分の1を7月の第1期と11月の第2期の年2回払いです。
第1期で控除しきれない場合は第2期に繰り越されます。
予定納税基準額は、確定申告書第一表「申告納税額㊾」欄に記載します。
扶養家族がいる場合は予定納税額の減額申請手続きを行う
扶養家族がいる場合は、「予定納税額の減額申請手続き」を行いましょう。
予定納税の減額申請手続きは、国税庁のホームページにある「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記入し、添付書類を揃えて期限まで税務署に提出します。
申請書には、年間所得や控除額、「申告納税見積額等の計算書」で計算した減額後の金額の記載が必要です。
ただし、「予定納税額の減額申請書」の提出期限は令和6年11月15日までです。
提出し忘れた場合は、確定申告時に手続きすることで定額減税を受けられます。
一人親方が定額減税を受ける方法【住民税編】
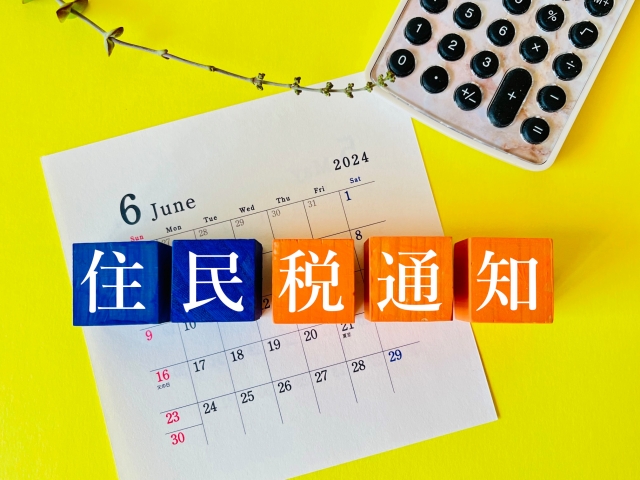
一人親方が住民税の定額減税を受ける際に特別な手続きは、必要ありません。
居住する自治体から送付される「住民税決定通知書」に記載される定額減税額を確認しましょう。
毎年6月、8月、10月、翌年1月と年4回に分けて納付する住民税の定額減税は、2024年6月から控除額が差し引かれて納付書が届きます。
従業員を雇用している一人親方は従業員分の手続きが必要
従業員を雇用している一人親方は、従業員分の定額減税手続きを行いましょう。
所得税と住民税の手続きに分けて解説します。
所得税
従業員を雇用している場合、所得税は年末調整で一括調整できないため、2024年6月以降、3万円の定額減税額を控除するまで毎月の源泉所得税から控除します。
従業員への給与明細や税務署や自治体へ源泉徴収票の提出時には、定額減税額を必ず記載しましょう。
もし、所得税を年末まで3万円を控除しきれなかった場合は、年末調整を通じて還付されます。
たとえば、源泉所得税が毎月7,000円の場合の定額減税のイメージは以下のとおりです。
| 2024年月別 | 源泉所得税 | 定額減税額 | 累計 |
| 6月 | 7,000円 | 0円 | 7,000円 |
| 7月 | 7,000円 | 0円 | 14,000円 |
| 8月 | 7,000円 | 0円 | 21,000円 |
| 9月 | 7,000円 | 0円 | 28,000円 |
| 10月 | 7,000円 | 0円 | 35,000円 |
住民税
住民税は、2024年6月分を除いた2024年7月から2025年5月まで定額減税後の税額で、11か月分に分けて毎月納付します。
住民税には年に4回に分けて住民税を支払う「普通徴収」と1年間の住民税を毎月の給与から天引きし、事業主が住民税を代わりに納付する「特別徴収」があります。
従業員の住民税は特別徴収が義務づけられていますが、金額は自治体が計算するとともに、個人事業主の場合は、特別徴収をしなくてもよいことになっています。
そのため、定額減税において必要な手続きはありません。
一人親方の定額減税に関するよくある質問

一人親方の定額減税に関するよくある質問についてまとめました。
定額減税で控除しきれない場合はどうなりますか?
住民税も所得税の予定納税と同様に、1期分で控除しきれない場合は第2期・第3期と繰り越されて控除されます。
定額減税で控除しきれない場合は、調整給付として2回に分けて別途支給される予定です。
2024年夏以降に「当初給付」、2025年以降に「不足額給付」が順次給付されています。
今後の調整給付の時期や申請方法は国税庁や自治体のホームページを確認しましょう。
赤字や所得税なしの個人事業主は定額減税できますか?
赤字や収入がなく所得がない個人事業主は、定額減税の対象となる税額がないため、定額減税の対象外です。
定額減税が適用されない住民税非課税世帯などの低所得者世帯には、給付金が別途支給されます。
対象世帯と給付金の内容については以下のとおりです。
| 対象世帯 | 1世帯あたり | 18歳以下の児童1人あたり | 給付日程 |
| 住民税非課税世帯 | 7万円 | 5万円 | 2023年末から順次 |
| 住民税均等割のみ課税世帯 | 10万円 | 5万円 | 2024年2~3月から順次 |
出典:内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
まとめ
定額減税は所得税3万円と住民税1万円の1人あたり合計4万円が減税される制度です。
扶養家族や従業員を雇用している一人親方にとって、税負担を軽減する定額減税は大いにメリットがあります。
個人事業主である一人親方は、基本的に確定申告で定額減税を受けられます。
定額減税の概要を理解して、扶養家族の申請手続きや従業員を雇用している場合は、所定の手続きを行い、定額減税制度を利用しましょう。
最新情報は国税庁や自治体のホームページを確認してください。
