「一人親方は常用契約と請負契約のどちらを選ぶべきなのか?」
「常用契約で働くと法律上問題はないのか?」
このような疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
常用契約と請負契約の違いが分からず、企業に提示された内容で契約してしまうと法律違反となるおそれがあります。
評価を下げず安心して仕事を続けるためには、契約内容を正しく理解し、リスクを回避することが重要です。
本記事では、常用契約と請負契約の違い、適切な契約方法、注意点を詳しく解説します。
一人親方として適正な契約を結ぶために、ぜひ参考にしてください。
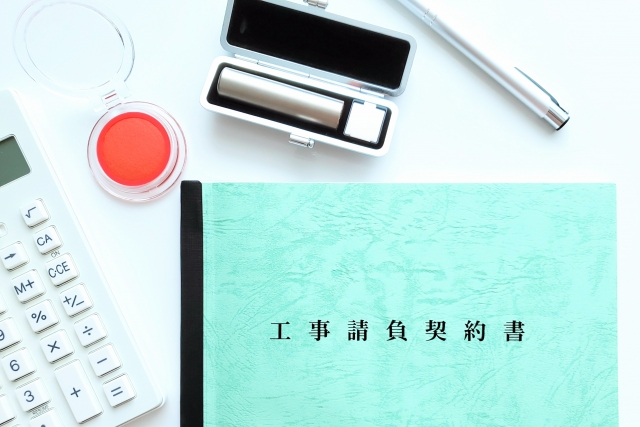
Contents
常用契約と請負契約の違い
常用契約と請負契約は、仕事を依頼する側と受ける側の関係性において異なる特徴があります。
常用契約と請負契約の違いを解説します。
常用契約
常用契約は、労働者として一定の期間、指示された仕事を実施することを目的として結ばれる契約です。
会社に雇用されている場合は基本的に常用契約となり、「9時~18時の勤務で、この業務を実施してほしい」というように、時間と業務内容が決められています。
常用契約では、雇用保険や社会保険などの福利厚生が提供されることが一般的です。
また、契約の時間働けば成果のいかんを問わず報酬が発生するため、収入が安定しやすいといえます。
しかし、報酬内容は人件費のみです。
交通費や材料費が含まれる請負契約と比べると、報酬は少ない傾向にあります。
請負契約
請負契約は、特定の仕事や成果物を完成させることを目的とする契約です。
請負契約をした場合、依頼された業務を自分の判断で進め、完成した成果物を納品することが求められます。
一人親方が請負契約をする場合は、「〇日までに△工事を完成させる。報酬は□円」といった内容の契約となります。
常用契約とは異なり、労働時間や勤務条件についての規定はなく、独立して仕事を進めるため、自由度の高さが特徴です。
また、報酬の支払い方法や業務の進行について、一定の裁量が与えられます。
報酬には、人件費以外にも仕事で使う材料費や交通費なども含まれるため、常用契約より高い傾向にあります。
しかし、期日までに仕事が完了できなかったり、完了した仕事にミスや不具合があったりしたら、責任を負わなければなりません。
加えて、社会保険や労働基準法の適用とはならないため、そのリスクを把握しておく必要があります。
一人親方は常用契約と請負契約どちらで契約する?
一人親方が契約できるのは、請負契約のみです。
常用契約は、企業に雇用される労働者が結ぶ契約であり、一人親方がこの形で働くことは法律上認められていません。
建設業では、注文者から直接依頼を受ける形式の「元請」と、注文者から依頼を受けた元請業者の一部または全部を別の業者(一人親方を含む)に依頼する形式の「下請」がありますが、どちらの形式でも、請負契約で結ぶ必要があります。
また、一人親方は個人事業主のため、社会保険料は自分で支払っています。
しかし、常用契約だと企業も社会保険料の一部を支払うため、一人親方が常用契約をすると矛盾が生じてしまうのです。
「時間も業務内容も指定してほしい」「社会保険料を支払ってほしい」という場合は、一人親方ではなく企業に属して働いた方がよいでしょう。
一人親方が常用契約をすることで起こるリスク

常用契約は、企業に雇用される労働者が結ぶ契約であり、一人親方の場合は法律上認められていません。
しかし、実際には常用契約に近い形で働く一人親方も存在し、「偽装一人親方」と呼ばれる問題につながっています。
ここでは、偽装一人親方のリスクを解説します。
法律違反となり処罰の対象となる可能性がある
請負契約をして、労働時間や業務内容が決められた状態で働くと、派遣とみなされる可能性があります。
建設業では労働者の派遣が禁止されています。
そのため、派遣とみなされた場合は、労働者派遣法違反となるかもしれません。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)違反となると、発注者と一人親方ともに1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
参照:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第59条
一人親方と取引先どちらの評価も下がる
常用契約を結ぶことで、一人親方自身や取引先の評価が下がる可能性があります。
特に、取引先企業が「偽装一人親方」と見なされた場合、行政からの指導や監査が入る可能性があり、業界内での信頼を失うことになりかねません。
また、一人親方自身も「独立した事業者としての信用」を損なうリスクがあります。
たとえば、ある一人親方が特定の企業と長期間常用契約を結んでいた場合、他の取引先からは「この人は本当に独立した事業者なのか?」と疑問を持たれる可能性があります。
その結果、新規の仕事を受けづらくなる、取引先の幅が狭まるといった問題につながるかもしれません。
評価が下がると仕事が受注できず、急に収入が途絶えてしまうリスクもあるため、最初から請負契約を結んで独立した立場を守ることが重要です。
一人親方の取引先が常用契約を結ぼうとする理由
本来、一人親方は請負契約を結ぶべきですが、企業によっては意図的に常用契約を持ちかけるケースがあります。
その理由を解説します。
社会保険料の支払いを少なくするため
企業が一人親方を請負契約ではなく常用契約のような形で働かせる背景には、社会保険料の負担を避ける目的があります。
企業が正社員を雇用すると、厚生年金や健康保険、雇用保険などの社会保険料を負担しなければなりません。
これは企業にとって大きなコストとなります。
一人親方は個人事業主のため社会保険料は自分で支払っています。
そのため、一人親方と常用契約を結べば、企業側は社会保険料を支払わなくて済むことになるのです。
企業側は実質的に社員と同じような働き方をさせながらも、一人親方という形式にすることで、社会保険料の負担を免れようとして、常用契約を結ぼうとする可能性があるのです。
労働関係法令の適用を避けるため
企業が常用雇用を持ちかけるもう一つの理由として、労働関係法令の適用を避ける目的があります。
正社員を雇用した場合、企業は以下のようなものを守らないといけません。
- 残業代の支払い義務
- 最低賃金の適用
- 労働時間の管理義務
- 有給休暇の付与
これらの義務を果たすためには、企業側の手続きの負担やコストが増加します。
しかし、一人親方と常用契約を結べば、これらの義務が発生しません。
そのため、企業は労働関係法令の適用を避けるために、常用契約のような形で一人親方と取引を続けようとすることがあります。
一人親方が請負契約を結ぶときの注意点

一人親方が取引先と契約を結ぶ際には、トラブルを防ぎ、自身の立場を守るためのポイントを押さえておくことが重要です。
契約内容があいまいなまま仕事を始めると、報酬の未払い、業務範囲の不明確さ、労働環境のトラブルといった問題が発生しやすくなります。
そうならないために、一人親方が請負契約を結ぶときの注意点を解説します。
口頭ではなく書面で契約を結ぶ
一人親方が契約を結ぶ際は、必ず書面で行いましょう。
口頭での契約は証拠が残らず、トラブルが発生した際に、報酬の未払いや契約内容の食い違いが生じる可能性があります。
たとえば、「〇〇の工事を完了させることで報酬を支払う」と口頭で約束しただけでは、工事が完了したあとに変更点を伝えられ、報酬なしでやり直しをしなければならないという事態になりかねません。
このような事態を防ぐためにも、契約書を作成し、業務内容や支払い条件を明確にする必要があります。
書面の契約が難しい場合は、メールなどの記録が残る形で契約内容を確認しましょう。
業務内容を具体的に記載してもらう
契約書には、業務内容を詳細に記載してもらいましょう。
業務範囲が不明確な場合、追加業務を押し付けられたり、想定以上の作業が発生したりするリスクがあります。
たとえば、「建築作業一式」とだけ書かれた契約書では、どの作業が含まれるのか明確ではありません。
その結果、後から「この作業も契約に含まれているからお願い」と言われ、追加の作業を求められる可能性があります。
そのため、契約書には作業の範囲を具体的に記載し、追加作業が発生する場合の料金設定も決めておくことが大切です。
報酬の支払い方法を確認する
請負契約では、報酬の支払い条件を事前に確認しておくことが重要です。
請負契約の場合、依頼された工事が完了したことに対して報酬が支払われます。
しかし、常用契約の場合は、日や時間あたりいくらで決まっています。
報酬の支払いが時給や月給となっていた場合は常用請負になる可能性があるので、必ず確認しましょう。
仕事で使う材料の準備や費用の負担が一人親方かどうか確認する
工事や作業を行う際に使用する材料や道具の準備・負担が一人親方側なのか、発注者側なのかを契約時に明確にしておきましょう。
請負契約の場合は、一人親方に一定の裁量が与えられているため、仕事で使う材料の準備や費用は報酬に含まれます。
しかし、常用請負の場合は、材料費などは会社負担となります。
請負契約といっておきながら、材料費などの負担が会社側だった場合は、偽装一人親方になってしまうおそれがあるので契約前に指摘しましょう。
指揮命令の有無を確認する
請負契約を結ぶ際には、取引先からの指揮命令の有無を確認することが重要です。
請負契約では、仕事の進め方は一人親方の裁量に任せられるのが原則ですが、実際には企業側が指示を出し続け、事実上の労働者として扱われるケースも少なくありません。
特定の企業の指示に従い、勤務時間が決められていたり、会社の指揮のもとで作業をしていたりする場合、偽装一人親方と判断されるリスクがあります。
契約時には、「仕事の進め方は一人親方の裁量で決められるか」を確認し、雇用関係に該当しないことを明確にしておきましょう。
まとめ
契約には常用契約と請負契約がありますが、一人親方が結べるのは請負契約です。
常用契約を結ぶと法律違反となる可能性があるため、注意が必要です。
しかし、社会保険料の負担や労働法の適用を避けるために、企業側が常用契約に近い働き方を求めるケースがあり、これが偽装一人親方の問題につながります。
契約を結ぶ際は、書面で交わし、業務内容や報酬の支払い方法、費用負担の明確化が必要です。
一人親方として適正に働くためにも、契約内容を慎重に確認し、リスクを回避する意識を持ちましょう。
